Use case
活用・成果事例

2025.8.26
コース別採用の課題を「社員インタビューAI」で解決。J:COMが実践するコンテンツ制作術
JCOM株式会社
事業内容
従業員数
・ケーブルテレビ局の統括運営を通じた有線テレビジョン放送事業及び電気通信事業
・ケーブルテレビ局及びデジタル衛星放送向け番組供給事業統括
グループ総計15,672名(2025年3月末現在)
事業内容
ITサービス事業、社会インフラ事業
従業員数
単独22,036名(2023年3月末現在)連結118,527名(2023年3月末現在)
導入目的
コース別採用におけるミスマッチを防止し、母集団形成と内定承諾率を向上させる
実施施策
戦略策定、記事制作、活用、分析
主管部署・担当
人事本部 人事部 新卒採用チーム チーム長 入江 健治氏
人事本部 人事部 新卒採用チーム 京谷 光氏、久保田 遥香氏
課題
- コース別採用の導入後、学生から「多様な社員の話を聞きたい」という要望に応えきれず、職種理解や入社意欲の向上につなげられていなかった
- 全国拠点の社員への取材は、日程調整やコスト面で物理的に困難だった
- 記事制作における企画・取材の工数がボトルネックとなり、新たな一手を打てずにいた
導入の決め手
- 全国の社員にリモートで取材できる、オンライン完結の「手軽さ」
- 「社員インタビューAI」が、記事本文だけでなく魅力的な見出しまで生成してくれる機能
- 一度制作すれば会社の魅力を伝え続ける「採用資産」となる、高い費用対効果
- 導入後わずか3カ月で18本というスピードでコンテンツを拡充
- 人事の工数を「依頼・校閲のみ」にまで削減し、持続可能な制作体制を確立
- 記事ページへのアクセスは非常に好調で、Googleなど検索エンジンからの流入が大きく増加
- SNS経由の流入増に加え、内定者フォローの質の向上にも効果を実感
コース別採用が本格化する中、JCOM株式会社様は学生に伝える「社員の生の声」が不足しているという課題を抱えていました。そこで、「手軽さ」と「社員インタビューAI」を決め手にtalentbookを導入し、スピーディーにコンテンツを増やすことに成功しました。その具体的な活用方法について、人事本部 人事部 新卒採用チーム長 入江 健治氏、京谷 光氏、久保田 遥香氏にお話を伺いました。
コース別採用で直面した、多様な「ロールモデル」を提示できないジレンマ
──まず、talentbook導入前の採用課題についてお聞かせください。
京谷さん:学生のキャリア観が多様化する中で、当社も職種別のコース別採用を始めました。専門人材の獲得と、学生とのミスマッチを防ぐのが目的です。そうなると、学生が次に求めるのは希望する職種で働く「社員の生の声」に他なりません。
説明会の内容は年々改善していましたが、面談などで「別の社員の話も聞いてみたい」という声が多く寄せられました。そこで、学生が求めているのは一つの情報ではなく「情報の種類の多さ」なのだと理解しました。営業職一つとっても、多様なキャリアを持つ社員がいます。そのバリエーションが不足していたのです。これまでは個別対応で面談を組むこともありましたが、手間がかかる上に、その場限りになってしまう。プラットフォームを通じて多様な社員の声をストックすることで、私たちが伝えている内容の「信頼度」を高めるアプローチが必要だと考えていました。
──生の声を届ける上で、どのような点に難しさを感じていましたか?
京谷さん:やはり記事制作の工数と、現場社員への負担が大きなネックでした。インタビューをしようにも調整が難しく、なかなか一歩を踏み出せない状況だったのです。
久保田さん:これまで、SNSで短い動画を発信することはありましたが、動画の尺には限りがあり、どうしても伝えきれない部分がありました。「記事という形式での発信も必要ではないか」という認識は、チーム内にもありましたね。
導入の決め手は「手軽さ」。全国拠点の取材課題を社員インタビューAIで解決

(左から)入江 健治氏、久保田 遥香氏、京谷 光氏
──数ある選択肢の中から、talentbookを導入された「決め手」は何だったのでしょうか。
入江さん:最大の決め手は、圧倒的な「手軽さ」です。当社は北海道から九州まで全国に拠点があり、たとえば従来の取材形式では、カメラマンやインタビュアーを伴って各地へ赴く必要があり、日程調整に多大な労力がかかっていました。
その点、talentbookはオンラインですべてが完結するため、この物理的な制約を解消できるのが画期的でした。加えて、talentbookの「社員インタビューAI」が自動で記事を生成し、私たちでは思いつかないようなキャッチーな見出しを付けてくれる機能にも、他にはない大きな可能性を感じました。
──導入決定にあたり、社内での議論はありましたか。
入江さん:はい、簡単な決定ではありませんでした。年度末の予算策定は、いわばチーム内でのコンペのようなもの。各担当者がエージェント活用やイベント出展など、さまざまな施策案を持ち寄って優先順位を議論します。その中でも、「talentbookへの投資は、今後の採用活動の“資産”になる」と強く確信し、導入を推進しました。
人事の工数を最小化。月5本更新を可能にした「仕組み化」の秘訣
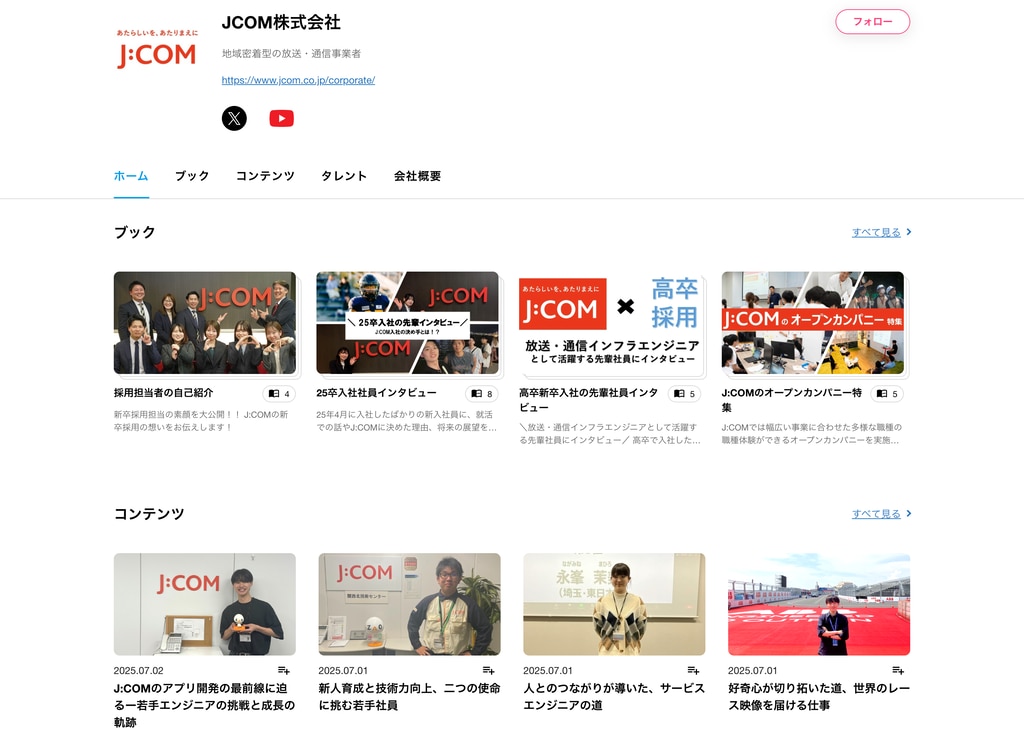
──導入後の活用についてお伺いします。
京谷さん:私がまず、年間を通じたコンテンツ計画の全体像を描きました。「毎月5本の記事をアップする」という目標を定め、大まかなスケジュールと各月のテーマを設定したのです。単発の施策で終わらせず、継続的な取り組みとして「点を線にする」ことを意識してデザインしました。
──その計画が、月5本という安定的な更新頻度を支えているのですね。
京谷さん:そうですね。また本格的に展開する前に、まず私たち採用担当者自身の自己紹介記事を作成することから始めました。ツールの使用感や制作にかかる時間などを自分たちで体験し、取り組むべきことを把握することが目的でした。この経験があったからこそ、説得力のあるマニュアル作成や、社員へのスムーズな依頼が可能になったと考えています。
久保田さん:当初は私たちもインタビューに同席していましたが、現在では社員本人に直接回答を入力してもらう形式に移行しました。そのための専用マニュアルも作成し、今では人事の工数は最終的な校閲のみで済んでいます。talentbookの「社員インタビューAI」がインタビュー音声を自動で書き起こし、読みやすい記事として整えてくれるので、助かっています。
──企画から公開まで、具体的にどのくらいの期間で行うのでしょうか?
京谷さん:たとえば、週の初めのチームミーティングで「今月は面接官の視点についての記事を作ろう」と決まれば、その週のうちに人選と依頼まで完了します。社員には2週間ほどで回答を入力してもらい、私たちの校閲を経て公開、という流れです。つまり、月の初めに企画すれば、その月末にはもう記事を公開できる。このスピード感が月5本という目標の達成を可能にしています。
──現場の社員の方々の協力体制も素晴らしいですね。
入江さん:それはコース別採用の導入が大きく影響しています。以前よりも人事と各事業部門が密に連携し、採用に対する課題感をリアルタイムで共有できるようになりました。そのため、記事作成を依頼した際も「採用のために必要だ」と快く協力してもらえます。以前は、多忙な現場社員に協力を仰ぐ際に調整が難しい場面もありましたが、現在は各部門が採用の重要性を深く理解しており、「ぜひ協力するよ」と前向きな姿勢に変わってきました。ここ1、2年で「会社全体で採用を成功させよう」という文化が根付いてきたと感じます。
久保田さん:記事制作を依頼する際も、社員への伝え方を工夫しています。たとえばオープンカンパニー参加者向けの記事では、社員に「『オープンカンパニー』というキーワードを意識的に入れてほしい」と、記事の目的を明確に伝えています。また新入社員には「多くの同期の代表として、後輩へのメッセージを届けてほしい」と、その役割の重要性を伝えるようにしています。意図を理解して協力してくれるので、コンテンツの質も上がっていると感じます。
アクセス増・内定者フォロー改善を実感。目に見える成果と、全社を巻き込む採用広報の未来

──実際に活用されて、どのような効果を実感されていますか?
久保田さん:talentbookで作成した記事をXでシェアしたところ、X経由でのサイト流入が昨年よりも確実に増加しています。また、内定者に対して、年齢の近い先輩社員の記事を送ることで、入社前の不安を和らげるフォロー施策としても有効に機能しています。
京谷さん:学生と接触した際に「この記事も見てみて」と提示できる「武器」が増えたことは、大きなメリットです。これは「ストック型のコンテンツ」として非常に価値があると考えており、今は効果検証よりも、とにかく記事のバリエーションを増やしていくことに重きを置いています。多角的な視点から当社を紹介することで、「この会社はこういう社風なんだな」ということを伝えるフェーズですね。
入江さん:数字の面でも、talentbookの自社ページへのアクセス数は非常に好調です。とくに、Googleなどの検索エンジンからの自然流入が大きな割合を占めており、関連するキーワードで検索した学生が、公式サイトの次に私たちの記事にたどり着いている状況です。これは、能動的に情報を探す学生層に、リアルな情報を届けられている証だと感じています。
──今後、talentbookをどのように活用していきたいですか。
京谷さん:短期的には、引き続き社員インタビューのバリエーションを増やすことに注力します。さまざまな職種やキャリアを持つ社員を紹介することで、学生の企業理解をよりいっそう深めていきたいです。中期的には、オープンカンパニーといったイベントの告知や採用選考の案内など、タイムリーな「ニュース」としての情報発信にも活用の幅を広げられると考えています。
──最後に、talentbookの導入を検討している企業へ「おすすめのポイント」を教えていただけますか。
京谷さん:talentbookの魅力はやはり「手軽さ」と「デザイン性」です。少ない工数で、専門知識がなくても洗練されたデザインの記事が作成できる点は、大きな魅力だと感じます。機能面では、記事をテーマごとにまとめられるブック機能が便利ですね。関連する記事を横断的に見せられるため、読者の興味を広げ、情報を整理して伝えやすいという利点があります。
久保田さん:私は「工数」と「費用対効果」を挙げます。本来であれば多くの調整を要する記事制作が、依頼から校閲という最小限の工数で完了します。また、外部に制作を依頼することに比べても、非常に安価に質の高いコンテンツを継続的に発信できる点は、他のツールにはないメリットですね。
入江さん:自社のホームページはたった1行の文章を修正するだけでも多大な時間とコストがかかることがありますが、talentbookを使えば、届けたい情報をタイムリーかつ手軽に発信できます。
だからこそ、採用広報に課題を持つ企業にとっては「使わない手はない」ツールだと断言できます。今後、talentbookが学生にとって当たり前に使われるプラットフォームになったとき、ここにコンテンツをいかに蓄積できているかが、他社との大きな差別化につながるはずです。今後の機能拡充にも大いに期待しており、将来的には採用活動だけでなく、社内の情報共有など、さらに多様な活用ができる可能性を感じています。

▼JCOM株式会社様のtalentbookページはこちら

